【iU B Labプロジェクト紹介】 アイデアや構想がもたらす付加価値を 言語化・可視化し大きくする
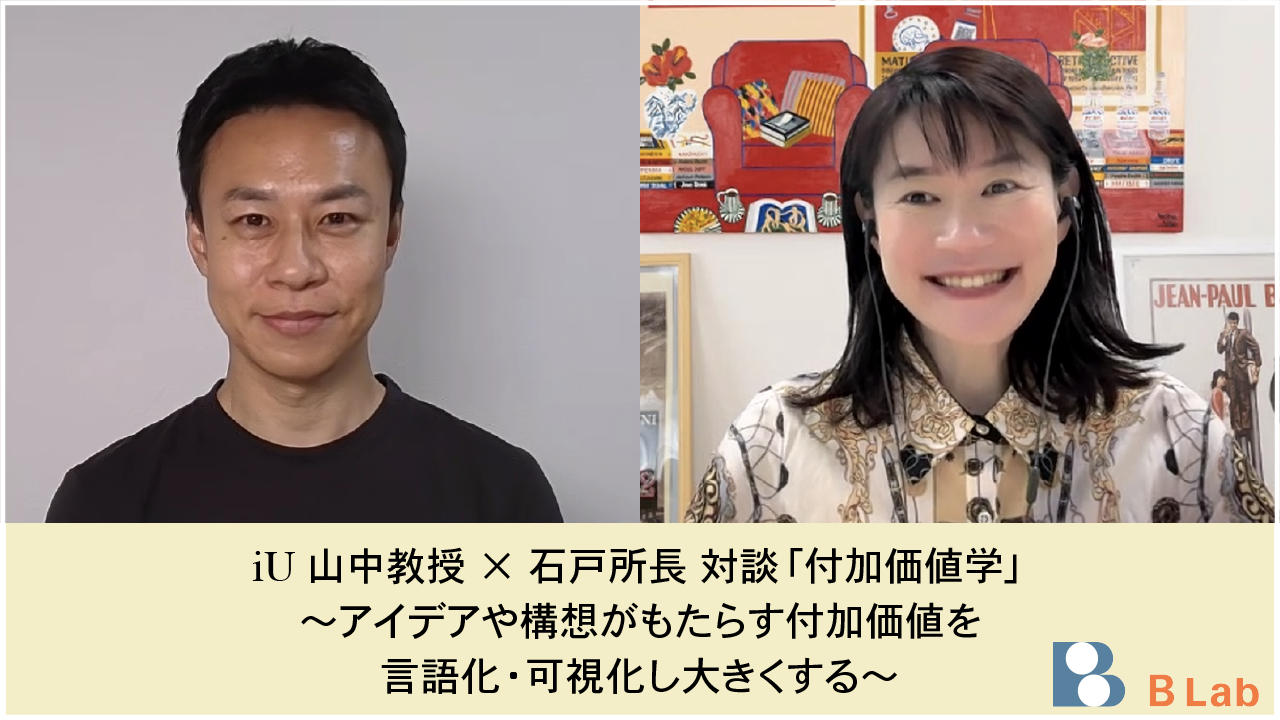
iUは、ICTやビジネススキルを活用して社会課題を解決し、世の中に新しいサービスやビジネスを生み出すイノベーターを育成する大学です。その研究所であるB Labでは、iUの教員が主導する多彩なプロジェクトが日々進行しています。
今回は株式会社トイトマ 代表取締役社長 山中 哲男 氏(▲写真1▲)にお話しを伺いました。山中氏が主導するプロジェクト「付加価値学」とは、日本が誇る地方の魅力やモノ作りの技術、新たなサービスなどの付加価値を言語化・可視化し、創出する手法を学ぶプロジェクトです。具体的にどのようなことを学び、それらを世の中にどう還元していくのか。B Lab所長の石戸奈々子(▲写真1▲)が、お聞きしました。
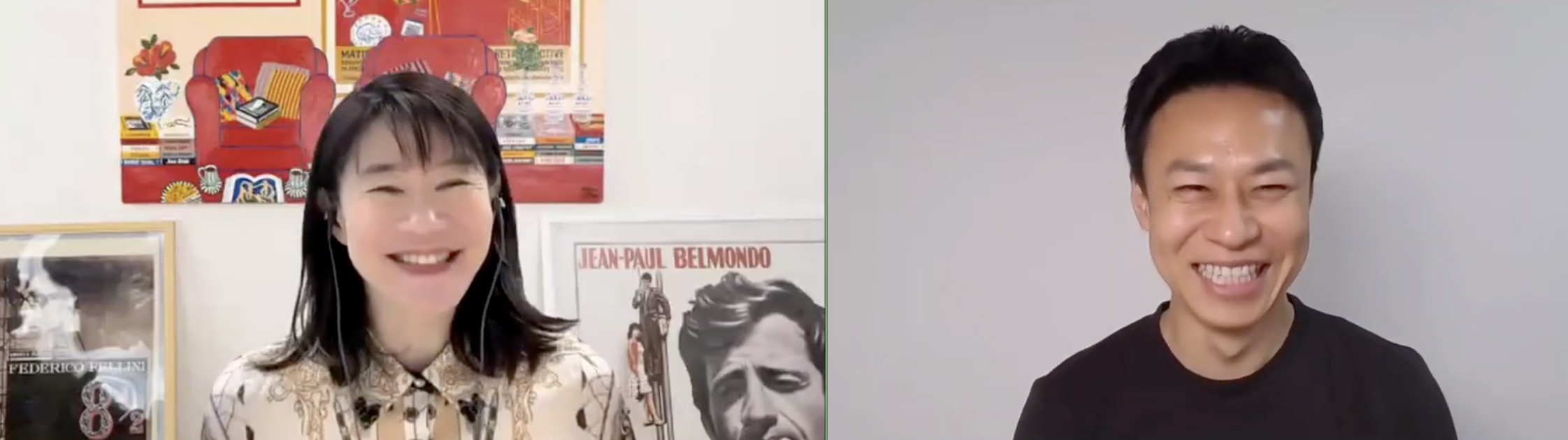
新たなアイデアや構想のなどの価値を言語化・可視化していく付加価値学
石戸:「山中さんは、事業開発支援・事業戦略立案を手がける株式会社トイトマの代表取締役としても活躍されています。そんな山中さんがiUでどのようなプロジェクトを展開しているのか、非常に興味深いですね」。
山中氏:「プロジェクト名は『付加価値学』です。付加価値はビジネスではもちろん、企画・研究・開発、また日々の暮らしの中など、さまざまな領域で創出されています。その付加価値とは何か、そこに着目して光をあてて、言語化、可視化しようというプロジェクトです」。
石戸:「確かに全ての領域で付加価値は創出できますよね。そこに光を当てたプロジェクトとのことですが、もう少し具体的にどのようなことをするのか、教えていただけますか」。
山中氏:「今や多くの企業や団体、個人などが、新たなビジネスや新製品など新しいモノを企画・立案し、世の中に広めていこうとしていますよね。私が普段、IT、飲食、医療などさまざまな領域での事業開発支援や事業戦略立案の支援を手がけている中でも、じつにさまざまな企画・構想・アイデアのご相談をいただきます。そうしたご相談の多くは、実際にビジネスを立ち上げたり、製品化したりしても『なかなか世の中に広まらない』というものです。それらに共通していることは、『自分たちにとっては、素晴らしいのに…』ということ。みなさん、『自分はすごく良いと信じているのに世の中に受け入れられない』とおっしゃるのです。
こうしたことが起きている理由の一つには、誰かが思い描いたアイデアや構想の価値が、世の中の多くの人に理解されていないことがあるでしょう。アイデアや企画・構想を社会実装していくためには、その価値を可視化しないといけないのです。しかも、そのときに大切なことは、価値とは『自分が決めるもの』ではなく、相手、つまり『世の中が決めるもの』だということを理解しておくことです。そこを置き去りにして、『とにかく良いものです』と主張される方々がとても多くいらっしゃいます。
しかし、自分目線で『これには価値があります』といくら主張しても、相手に価値を感じてもらわないと社会実装できません。そこで、プロジェクトでは、さまざまなアイデアや企画について『誰がその価値を感じるのか』を言語化することに取り組みます。そのうえで、付加価値とは何かを考えます。『価値とは相手が決めるもの』という考え方を根底に置いて、特定の人たちを対象に課題や成し遂げたい目標を解決したり、実現したり、それらができるように補足したりするもの、それらを総称したものが『付加価値の領域』だと考えています。こうした考えのもとに、プロジェクトを通じて個人や企業、団体が思い描くアイデアや構想を世の中に広げていくための接続点を作っていく、しっかりと価値という言葉を通じてそうした取り組みを実践していこうと考えています」。
石戸:「なるほど。『独りよがり』ではうまくいかないのですね。山中さんは、事業開発支援や事業戦略立案といった仕事を通じて、さまざまな付加価値の創造に成功されていらっしゃいます。これまでの取り組みの中で、ビジネス領域での成功事例、自治体など公共領域での成功事例を教えていただけますか」。
山中氏:「私は飲食業界出身なので、飲食業界での成功事例をお話しします。メディアにもよく取り上げてられていますが、丸亀製麺の支援事例がわかりやすいでしょう。丸亀製麺をご支援したときには、同社の若手の社員などを含め、多くの社員の方々と『価値とは何か』について語り合いました。
先ほども申し上げましたが、価値とは相手が決めることです。その視点に立ってさまざまに考えて議論した中で、丸亀製麺の付加価値とは『ランチでみながお腹を空かせたタイミングで、出来立て手作りの食事が提供されること』となりました。これは何を連想させるかというと、子供の頃の出来事ではないでしょうか。夕方に家に帰って6時頃になるとお腹がペコペコになり、そんなときに『ご飯できたわよ』と言われて食べると、それが豪華かどうか別にして、ものすごく美味しいでしょう。ところが、大人になって一人暮らしをするようになると、こうした体験はなかなかできなくなります。丸亀製麺の体験価値は、そういった出来立て、手作りの大衆食文化を再現しているところにあるのです。
わざわざお店で手作りして目の前で作った食事を提供するという体験価値は、お客様からするとありそうでないことです。セントラルキッチンが浸透し、個食化、インスタント化していますが、丸亀製麺はその中であえて手作りで出来立てを提供することで、『お腹が空いた時に食べた体験』を思い起こさせるような『値段以上の価値』を実現しているのです。こうした取り組みを、丸亀製麺の社員の方々と一緒に言語化しながら進めてきました。参考になると思います」。
石戸:「地方創生などにも取り組まれていますが、公共領域ではどのような事例がありますか」。
山中氏:「私が手がけている地方創生は、ある古民家を再生するような取り組みではなく、ある地方に新たに建物を10施設や20施設ほどまとめて開発するような面的開発が中心です。その時の付加価値には、2つの目線があります。1つは地域住民たちの目線、もう1つは顧客目線です。公共領域での取り組みでは、まず地域住民たちの目線、地域目線の取り組みが大切で、地域の人たちが遊びに行くことができる、地域の人たちが働きに行ける場を作るというように、相手目線で物事を考えることを心がけています。最近の地方創生ではホテルも含めてラグジュアリーな施設の新設も見受けられます。そうした施設ができることは、地域も嬉しいとは思いますが、地域住民がそこで働けるのかというと、必ずしもそうではありません。
お客様の視点で考えても、例えば1泊30万円もするような高額のホテルだと、地域の住民はなかなか泊まることができません。地域からは遠い存在になってしまいます。そうではなく、もっと地域目線で考えていけば、地域住民が泊まってみたら素晴らしい体験ができたので、それを自分の家族にも宣伝して息子や娘に『あそこで働いてみたら』と勧めるような派生的な効果もでてくると思います。地域目線で考えると、地域住民が働ける、地域住民が遊びに行ける、結果として誇りや自信という付加価値が創出され、それが世の中に受け入れられていくのです。こうした意識を持って、さまざまなエリアで地方創生や地域開発を手がけていこうと考えています」。
「誰にとって」の付加価値なのかを徹底的に追及する
石戸:「付加価値を創出できる人材が増えると、さまざまな社会課題も解決できますし、新しい創造的なプロダクトやサービス、ビジネスなども生まれてくると思います。山中さんのプロジェクトは、『付加価値学』と名付けたように学問であり、付加価値を創出するメソッドについても学ぶのだと思います。そのメソッドのエッセンスを教えていただけますか」。
山中氏:「先ほど、価値は相手が決めるものとお話ししました。ですから、価値を見出す時に最も重要となるのは『相手』、つまり、顧客です。誰を顧客とするのか、この『顧客の特定』が曖昧なケースがとても多く、意外とみなさんができていません。メソッドとしては、顧客特定を徹底的にやるところが、まずはスタートだと考えています。これができていない中で、『どうやってこのアイデアを広げようか』、『どうやって届けようか』と考えてもなかなか難しいのが実情です。
顧客を特定するには、価値は相手が決めるものという考えに基づいて自分たちがやろうとしていること、自分たちのサービスやプロダクトは『誰にとって喜ばれるものか』を徹底的に考え抜く必要があります。具体的な方法としては、自分たちだけで勝手に『この人たちに喜んでもらえるだろう』などと妄想するのではなく、しっかりと現状や実情を知るためにヒアリングやインタビューなどを手間暇かけて実施し、面倒なことを繰り返しながら顧客を特定していきます。
顧客が特定できない中では、ブランドの発信などといった領域には一切、手を付けません。並行してやればいいと思う人もいるかもしれませんが、顧客が特定できないうちに手を付けると『やっているのに広がらない』というストレスがどんどん蓄積していって、『自分たちは良いと思っているけれども、多くの人たちは求めていないのではないか』とモチベーションが下がってしまうことがよくあります。
繰り返しになりますが、最初に顧客を特定することに徹底的にコミットすることが大切です。ここに取り組みながら、付加価値を100パーセント言語化できているかについて考えると、まだまだ解像度を上げないといけないところもあるでしょう。プロジェクトでは、関係してくれる学生や関与してくれる企業も含めてさまざまに対話しながら、しっかりと解像度を高めて言語化していきたいと考えています」。
石戸:「公共領域、パブリックな取り組みでは、取り組みそのものに意義があり認知も広がっているものの、持続的に運用するための資金を得る仕組みがうまく作れないケースも多くあります。社会的な意義と持続的運用とのバランスの取り方が難しいと感じています。プロジェクトでは、こうした課題にどのように対処するのでしょうか」。
山中氏:「パブリックに向けば向くほど、参加者や参加企業のマインドが『自分たちは稼ぐためにやっているのではない』、『ザ・ビジネスのスタートアップとは違う』という方向に向くようになると思います。とはいえ、プロジェクトや取り組みをサステナブルにしようとすれば、一定程度、稼ぐことも必要です。ご指摘の通り、そこが課題にはなってきますね。
まずやらないといけないのは、自分たちがこの新しい事業や取り組みを運営していく中で『いくら必要なのか』を参加者全員がしっかりと認識することです。それができないままでは、自分たちの活動費用すらも捻出できませんし、未来の投資もできません。そのうえでさらに考えると、資金だけが潤沢にあっても持続的な取り組みにはなりません。そこで、私が最初に考えるのは『リソースの確保』です。このアイデアを発展させ、世の中に浸透させていく事業や取り組みを実装していくのに必要なリソースです。
私はお金だけ、資金だけの指標は作りません。『資金・役割・スキル』の3つのリソースを考え、それぞれの目標値を立てて考えます。例えば資金が足りなかったらどうやって捻出するか、スキルが不足していたら外部のパートナーを募るなど、どうやって補うかといったことを決めていきます。この3つの視点からプロジェクトの解像度を高め、それをコアメンバーで共有し、現在の状況を全て理解するところから始まると思っています。
解像度を高めないと、必要な資金がいくらかすらわかりません。ただ『稼ぐ』という目標は非常に曖昧ですが、例えば『このスキルが足りないからパートナーを採用する、そこで30万円必要』とわかれば、そこにピンを立てていくことで大体の数字が見えてきます。『このアイデアを広めるためには、稼がないといけないよね』というざっくりした会話の中で、『でも稼ぐということはさ…』という議論を具体化していくことが突破口になるはずです」。
『付加価値学』を大学で提供することの意義とは
石戸:「付加価値を創出するという取り組みを公益法人などではなく、大学でやることの意義をどのように捉えていらっしゃりますか」。
山中氏:「学生が参画することに大きな意義があると思っています。1つの『学』として提唱していくためには、再現性も必要で学生の視点で分かることが必要です。さらに、言語化しメソッド化していくには、学生の視点が重要だと思っています。今、まさにiUのプロジェクトで実践しているところで、学生たちにはビジネスアイデアを出してもらっています。
学生たちをチームごとに分け、自分たちの取り組みにはどういった付加価値を付けられるのか考えながら、検証、ヒアリングなどに継続的に取り組みます。どんどん行います。私自身も、学生たちに伝えるための言葉を自分で整理できるようになります。学生たちからも次々に質問されますので、対話の中で解像度を高めていくことが大学を通じてできると感じています。
もう1つ、iUは学生より客員教員の方が多いところがとてもユニークです。先ほど何かを実現しようと考えたときにはリソースの確保が大切であるという話をしましたが、何か新しいことをやろうとするとスキルや役割など足りないリソースが見つかります。そうしたときに1000人以上いる客員教員を含めたiUのプロフェッショナルのネットワークを活用できます。ラボ型プロジェクトを学生と一緒に行いながら対話式でリサーチして形にし、プロ型のプロジェクトができたら素晴らしいと考えています。客員教員たちが一緒に共創しながら価値を見出していくことも、さまざまな専門分野やスキルを持った人たちがいることによって実現できるでしょう。この2点が大学でできることの面白さと思っています」。
石戸:「山中さんのようなことができる人材が増えたらイノベーティブな社会になるだろうと感じます。大学で取り組むことの意義としては、ビジネスとしては手を出しにくい領域、例えば社会起業などの領域において、長期的な目線で物事を捉えて取り組むことができるという点があると思います。パブリック領域においてさまざまな付加価値を届けるプラットフォームという役割を大学が果たすと良いと思いますし、大学をハブにして、スキルやナレッジ、人材、資金など新しい価値を生み出すのに必要なリソースがマッチングされていく、そんな場に大学がなっていくようにB Labも育てていきたいと考えています。こうした取り組みを実践するにあたって必要なことは、何であるとお考えですか」。
山中氏:「わかりやすいロールモデルを作ることだと思っています。例えばB Labで実現できるモデル、しかも分かりやすいモデルがあると、『自分たちもここを使ってみようかな』、『自分たちもここに登録してみようかな』と広がっていくのではないでしょうか。最初はアイデアや構想から入ると思いますが、アイデアや構想からモデルを見える化できれば、『こんなことができるのか』、『こんな可能性があるのか』と思うようになるでしょう。
現在は一人で何かを成し遂げるというよりも、『誰かと何かを成す』、『足りないところは補う』というような共創社会の方向に向かっていると思っています。B Labがそのような社会のハブになると素晴らしいと思っており、そのわかりやすいモデルをいくつか作って発信し、アンテナを張っている人たちとの出会う中で、さらにその輪が広がっていくでしょう。
プラットフォームとして成功するポイントは、『あれもこれもできます』と言わないことだと思っています。Amazonなど成功しているプラットフォームは一点集中型でターゲットを絞り、その中で価値を感じてもらいファンを増やして横展開し、結果的により大きなプラットフォームになっています。それが正しいあり方だと思っています。『あれもこれもできます』というよりも、まずは『これができる場です』とモデルケースを示し、その延長線上の結果として、2~3年後に大きなプラットフォームになっている、それがB Labであれば良いと思っています」。
地域や地方にはポテンシャルがある眠っている価値に光を当てる
石戸:「山中さんとはぜひ今年度中に3つぐらい、モデルケースを一緒に創出できたらと思います。私もiU教員の共創事例をもっと作りたいと思っています。それぞれの領域で既にプロフェッショナルとして活躍している方々同士の、ここでしかできないコラボレーションを創出する中で付加価値を2倍、3倍にしていきたいです。
そんな共創に一緒に取り組むとして、山中さんが関心ある領域はどこでしょうか」。
山中氏:「地域が1つのキーワードです。地域に関連しては優れたものがたくさんあるのですが、なかなかそこに光が当たっていないと感じています。観光、モノ作りなど、さまざまな分野で素晴らしいものがあるので、そこに光を当て価値を見出せるような取り組みをしたいと考えています。
これまでの観光業では、旅行代理店がマーケティングやPRをしてきました。それが今では、自分たちでマーケティングやPRをしないとならない時代です。ようは観光業界はウリが見つからない状況です。モノ作りについても受託事業をずっとやってきたことでノウハウは溜まっていますが、そのノウハウや資材を使って何か新しいモノを作っても売れないという現実があります。
つまり、観光もモノ作りも受託事業者だったことから、ウリをうまく作れなくなっているのです。それは農業も同じです。作ることに専念していた人たちが、価値を見出せるような世の中になっていくと理想的です。地域には『作れるのにウリを見出せない』という事業者や個人はたくさんいます。そこにもっと光を当てることによって、それらが地域の自信や誇りを持ち、そこに関わる人たちの自信や誇りになっていく、『自分たちにもこんなに良いところがある』と思えるような世の中を作れたらと考えています。地域をキーワードにして、何か価値を見出していくようなことができると嬉しいですね」。
石戸:「とても興味深いお話しです。山中さんは、地方に眠っているような顕在化していない価値に気づくための手法をお持ちですか」。
山中氏:「自分たちが良いと思っていても、それは何が良くて誰にとって良いのかがわからないというのが現状です。そんな状況の中では、もっともシンプルなのは関係性のない人たちに率直に聞くことだと思います。聞くことは知ることです。相手がどう感じるのかを知り、把握していかないと、それ以上の深堀りはなかなかできません。自分が良いと思うことは、ひとまず横に置いておいて、単純にさまざまな人に使ってもらったり、体験してもらったりします。観光でもよく言われることですが、『よそ者の目線』を取り入れることで、『こんな人が喜んでくれるんだ』と発見することは良くあります。
ハッと思わされるようなことは、自分視点ではなく相手目線から生まれることがほとんどです。自分だけが感じている良いモノを世の中に顕在化させるためには、まずはさまざまな人たちから情報をもらい、あれもこれもではなく特定の層を決めて、良いと思っていたモノが特定した人たちに喜ばれるモノになっているかを見直し、もう1度、アップデートしてみるのです。表現の仕方やデザインなども含めて、さまざまなことが考えられますが、特定の人たちが最も喜ぶモノにアップデートして提供していきます。そこから、さらに、あれもこれもとはならないように優先順位を付けて取り組んでいきます。
結果として、どんどん広めていくのはいいのですが、まずはターゲットを絞り、その人たちに喜んでもらうこと。そして、『お金を払ってでも欲しい』という人たちを見つけることが大事ですので、そういった人たちをリサーチして特定していきます。面倒ですが、AIではまだ精度高く特定できるとは言い切れないでしょう。手間も時間もかかりますが、さまざまな人たちに聞いて、現状を知ること、それがまずはできることです。そうした取り組みを通じて価値に気づくようになると思っています」。
石戸:「さまざまな人に聞いてみる、相手の目線で見る、ということでは共通するのかもしれませんが、地域の人たちも気づいていないところに実は価値があるというようなやり方も大事なのかと思います」。
山中氏:「さまざまな地域の人たちに、『地域の活性化をしたい』と呼ばれることがあります。地方創生や観光に関することが多いのですが、その中で『山中さんの目線で自分たちの良さはなんですか』と聞かれることがあります。
地域の人たちが自分たちでも気がついていない価値に気づくには、単純に地域のあるモノに触れてもらう、その地域に『来てもらうこと』だと思います。いきなり見知らぬ人に『来てください』とお願いしてもなかなか来てくれないことを考えると、来てもらうためには人との繋がりが大事だと考えています。
そこで、まずは地元の出身者に声をかけてみるなど、身近な縁がありそうなところからお声がけをして来ていただくのがいいと思っています。デジタル社会の今でも事業を展開していくためには『知る』こと、『聞く』ことを重視していますし、自分たちのモノの価値を見出してくれるような人に1回は体験してもらっています。それがいいか悪いかは置いておいて、人の繋がりの中で価値は見出されていきますし、価値が広がっていくと思っています。
人の繋がりをうまく活用していくことはネクストステップに繋がる大きな要因だと思っていますので、一人で悶々と考えながらインターネットで調べるのも良いですが、思い切ってそれを誰かにぶつけてみることも大切です。下手な説明でも、間違っていてもいいのです。その結果、『魅力については、よくわかりません』ということもあるでしょう。それでも人との出会いや繋がりを大事にして、広げていくことを日々行っていくと、パブリックなモノであってもスタートアップ的な成長型であっても人の繋がりが価値を見出して広げていく後押しになる、その機会になるのだと分かってきます。そこを軸にできるといいと考えています」。
石戸:「まさにそれこそが共創のきっかけになると思います。大学を、多様な立場の方々をより多く巻き込みながら、常に相手目線を忘れずに付加価値を生み出す場にしていきたいです。最後に、社会に向けて、それから産業界に向けて、一言メッセージをいただいてお終いにしたいと思います」。
山中氏:「私は、まだまだ日本には誰かが喜んでくれるモノが眠っていると思っています。私もさまざまな相談を受ける中で、『こんなことが世の中であるんだ』、『こんなことを考えている人がいるんだ』と痛感する機会が多くあります。つまり、まだまだポテンシャルがあるのです。
まだ光が当たっていないポテンシャルを社会と接続して実装するために私自身も取り組み、そして今回、B Lab、そしてiUのさまざまな繋がりを使って実現していきたいと思っています。私は自信や誇りという言葉を使いましたが、『日本ってダメだよね、遅れてるよね』と卑屈になるのではなく、実はポテンシャルがあるところにもしっかりと目を向けて、そういったモノが世の中に広がっていくことによって、一人でも多くの人が自信や誇りを持てる社会にしていきたいと思っています。付加価値学というプロジェクトを、そういう視点でみなさんと一緒に世の中を盛り上げていくきっかけ、機会のひとつにしていきたいですね」。
石戸:「ありがとうございます。B Labでも今年度中に山中さんとロールモデルになる共創プロジェクトを立ち上げたいです。興味があるみなさん、ぜひご連絡ください」。
