【iU B Labプロジェクト紹介】 スマホで楽しむ1分間の縦型ショート動画をAIを活用して量産し映像業界にイノベーションを
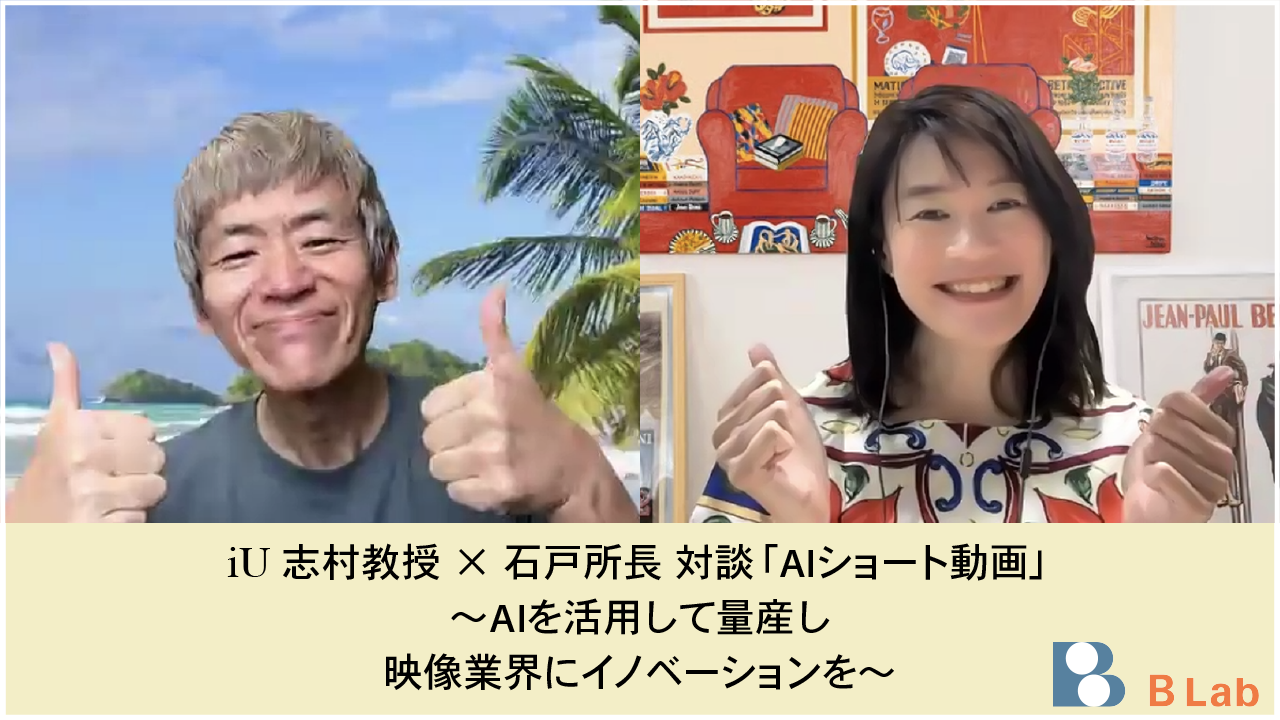
iUは、ICTやビジネススキルを活用して社会課題を解決し、世の中に新しいサービスやビジネスを生み出すイノベーターを育成する大学です。その研究所であるB Labでは、iUの教員が主導する多彩なプロジェクトが日々進行しています。
今回は、吉本興業グループ 株式会社FANY取締役でiU基幹教員の志村 一隆氏(▲写真1▲)にお話を伺いました。志村氏が主導するプロジェクト「AIショート動画」とは、AIが書いたシナリオをもとに1分間のショート動画を撮影し、その動画をAIでアニメ化する取り組みです。「隙間時間」で視聴できるショート動画を「時短・量産」することで、映像業界にイノベーションを起こすことが期待されています。具体的にどのようなプロジェクトが進行しているのでしょうか。B Lab所長の石戸奈々子(▲写真1▲)が、お聞きしました。
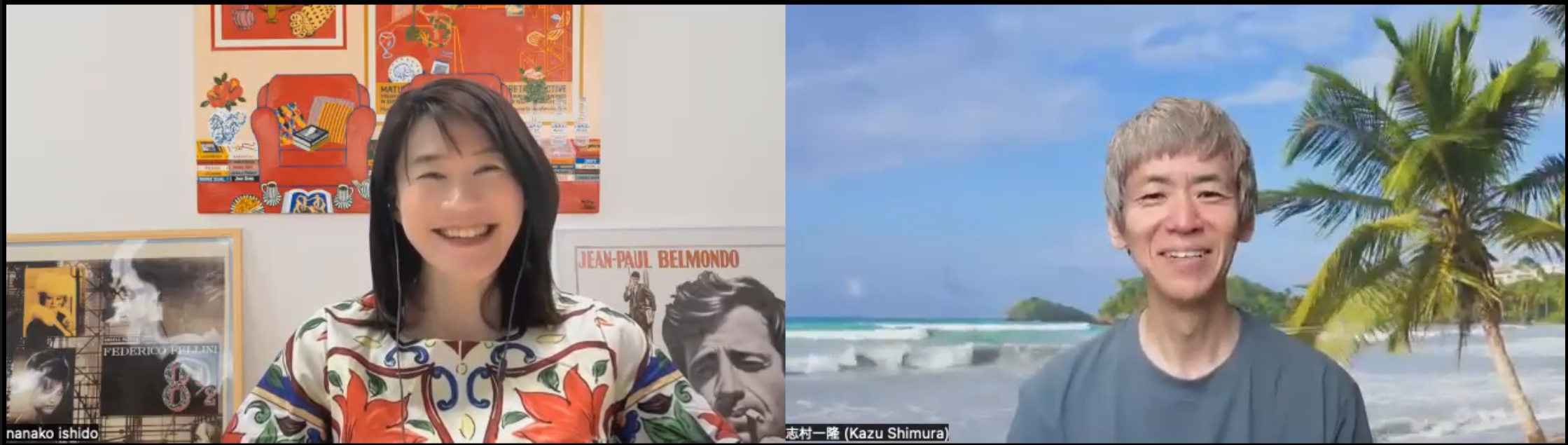
AIが書いた脚本をもとに縦型ショート動画を作りアニメ化する
石戸:「志村さんは、吉本興業の取締役を務めつつ、iUでは教員としてプロジェクトを率いていらっしゃいます。どのようなプロジェクトなのか、詳細を教えていただけますか」。
志村氏:「プロジェクト名は『AIショート動画』です。今や多くの人たちがスマートフォンで縦型ショート動画を視聴して楽しんでいますよね。あのような縦型ショート動画(ドラマ)をiUのスタジオや校舎を使用して作っています。最初は企画・脚本を作り、実写で撮影して編集してショート動画を制作していたのですが、今ではAIを取り入れています。企画・脚本をAIに作ってもらい、それをもとに実写を撮影し、さらにAIで実写をアニメ化するところまでをやろうとしています」。
石戸:「AIもショート動画も注目のキーワードです。志村さんが、このプロジェクトをiUで始めようと思った背景は、どのようなことだったのですか。志村さんがどのような課題意識をお感じになっていたのか、お聞かせください」。
志村氏:「このプロジェクトに取り組もうと思ったきっかけからお話しします。iUの敷地内には『BSよしもと』と提携したスタジオがあり、スカイツリーというシンボリックな建造物を楽しめるビュー(景観)もあります。また、iUの校舎は非常に新しく、撮影していて『映える』場所が数多くあります。せっかくなので、これらを利用してショート動画を作ってみたらどうだろうと始めました」。
石戸:「AIショート動画は、縦型画面で作られていますよね。多くの人が楽しんでいますが、一方でスマートフォンは使うが縦型動画はあまり視たことはない、馴染みがないという人もいると思います。これまでの映像とは、何がどう違うのでしょうか」。
志村氏:「まずは画角が違います。これまでの映像は一般的に横型で、幅が横方向に拡大してきました。もっとも幅広の映像は、IMAXや映画館の画角だと思います。そこにスマートフォンが普及してきたことで、TikTokやYouTubeショートなど、スマートフォンで見る・視るといった行動様式に合わせた縦型の動画が作られるようになってきました。スマートフォンでのエンタテインメント・コンテンツといえば、これまでゲームが中心でしたが、通信速度や機能の向上などで現在では動画視聴が一般的になっています。しかも、わざわざ横にして視るのではなく、『横型に思い入れのない若い世代』が縦型で楽しんでいます。このように映像の画角、フォーマットが違います。
もう1つの違いは、視聴スタイルの違いです。クリエイターからすると思い入れを持って作り上げるのが映像作品ではありますが、その作品を視聴するスクリーンが今やスマートフォンの画面になりました。しかも、どこで視聴するかというと電車での移動中などの隙間時間です。つまり、『隙間時間で消費する』視聴スタイルに変化しているのです。ここがこれまでの動画とは違います。
しかも、視聴スタイルが大きく変化している中にあって、そこに特化した動画がまだ少ないのが現状です。メディアの変わり目に大きなビジネスチャンスがあるのに、そこに特化したショート動画が少ないのです。そこでスマートフォン向けの縦型動画で隙間時間に視聴できるコンテンツを作ろうとプロジェクトに取り組んでいます」。
石戸:「メディアのフォーマットが変わったり、受け手の視聴スタイルが変わったりすると、それに合わせたコンテンツの表現も変わってくると思います。志村さんが説明された画角や視聴スタイルに合う表現は、これまでの動画での表現と比べてどう違ってくるのでしょうか」。
志村氏:「ショートという言葉が象徴的ですが、動画1話が1分間という短い時間で終わるように構成されています。これまでの動画で長いものといえば映画です。最長2時間程度になります。テレビドラマは30分から60分です。これらと比べると、1分という非常に短いフォーマットで、さらにその1分を30話ぐらい繋げて最終的にエンディングまで持っていきます。
2時間や60分、30分の映像では、最初の3分、もしくは1分がシナリオの導入部となり、どうしても展開がスローになりがちです。それに対し、1分に区切ることで、その1分の間に次のエピソードに視聴者を誘導するような、業界用語でクリフハンガーと呼ばれる仕掛け、次へとつなぐきっかけを入れていくというようにシナリオの作り方も変わってきています。
さらに、長尺の映像では3秒で変わるカットや、長回しで何分も同じカメラで撮るカットがありますが、ショート動画は1秒1カットが基本で、1分間の間に60回ぐらいシーンが変わるような作り方をします。こうした作り方をすることで表現の仕方も当然、これまでの映像・動画とは異なってくるのです」。
石戸:「実際、学生のみなさんと作ったショート動画を観せていただけますか」。
志村氏:「AIショート動画のゼミのTikTokにアップしています」。
原作をアニメ化し、最後に実写版を作るこの流れがAI活用で逆転する
石戸:「志村さんのプロジェクトでは、ショート動画にAIを使うのが特徴的です。どのようなところにAIを使っているのですか。また、AIを活用することで制作がどのように変わってきていますか」。
志村氏:「量と時短の2つがキーワードです。まずは、企画・脚本の作成にAIを活用しています。通常、1分の動画を作成するのにA4サイズの用紙2~3枚分のシナリオが必要です。これまでは、ゼミ生が週2時間、集まってシナリオを作成していましたが、3週間かけて1~3本程度しか作れませんでした。ところが、AIで作ると量産でき、キーワードなどを入れて指示するとすぐに30本程度は作成できます。つまり、シナリオの基礎となる脚本アイディアが量産できるのです。シナリオ作りはAIに任せて、そこから人がピックアップしていくというように仕事のやり方が変わるのです。
量が作れるので時短にもなり、わざわざ時間を合わせて集まることも必要なくなります。個人がAIで30本作ってきて、その中から良いシナリオをピックアップしていきますが、ピックアップもAIに任せることもできます。ショート動画の企画から完成までのリードタイムが非常に短くなるのが大きなイノベーションです」。
石戸:「これから映像業界に、AIはどのぐらいのインパクトをもたらし、どういった影響を与えていくと考えていらっしゃいますか」。
志村氏:「どの業界も同様でしょうが、人が行う作業をAIが代替していくことになると思います。現在、海外から日本へのコンテンツ需要は、そのほとんどがアニメです。そこで、日本でアニメを作ろうとすると、国内のアニメ制作現場は『4年先まで埋まっている』と言われているので、例えば、注目された実写をアニメ化しようとしても完成するのは何年も先になってしまいます。そこが、アニメ制作のボトルネックとなっていると思いますが、AIを活用することで、量を作れるようになります。実写からアニメを制作するコストも、これまでの4分の1ぐらいに抑えることができます。量が作れるということは時短になるということで、コストも安くなるということです。
また、これまでは、映像の前にテキストの小説や漫画の原作を映像化することが、エンタテインメントのウィンドウ戦略でした。これは、制作にかかるコストを考えると、テキスト、つまり小説などの原作にかかるコストが最も安価で映像が最もコストがかかります。できるだけリスクを減らすために、ヒット作でコストの安いコンテンツをピックアップして、次のウィンドウである映画や映像を作るという戦略だったのです。この戦略がAIによって逆転するようになりました。
これまでは、漫画があり、その後にアニメを作って実写という流れでしたが、それが変わって、まずは実写を作り、それをAIでアニメ化するというビジネスモデルとなりました。キャッシュポイントが真逆になってきているのです。これも非常に大きなイノベーションかと思います」。
石戸:「映像業界に与えるインパクトについてお話しいただきました。冒頭、吉本興業の話もありましたが、産学連携についてもお話を伺いたいです。実際に吉本興業やその他の企業とコラボレーションしながらプロジェクトを推進されていらっしゃるのですか」。
志村氏:「これから募集中です。実際、1、2社の企業とコラボレーションしたのは、動画の運用においてです。今は自分たちで作った動画を自身のアカウントにアップするという動画の運用においても、ビジネス上で非常に大きなニーズがあると感じています。コンマ1秒ごとに1回、アップして『どうやったらバズるか』を研究し、その実績をもとに企業から依頼されたショート動画を制作しています」。
石戸:「各企業でもAIの使い方の模索や新しい表現様式に対する試行錯誤を行っていると思いますが、志村さんが考える大学だからこそできること、大学だからこその良さはどのようなところにありますか」。
志村氏:「表現方法という視点では、まず、20代前後のZ世代が感じて作る制作面のセンスが発揮されることでしょう。また、若い世代をキャスティングできるという優位性を感じています。ショート動画の利用者がこれから増えていくと、さまざまなセグメントに広がっていくとは思いますが、今のところは若い世代のキャストが画面に出ていた方が『バズる』傾向にあると言えます。その視点でのキャスティングの優位性が大学にはあると思います」。
石戸:「若い学生たちと一緒に制作をしていて、感性や感覚の違いで驚くようなこともあるのですか」。
志村氏:「日々、驚かされています。若い学生たちには、やはり伸び代がありますね。授業やゼミで講義を受けているときと、ショート動画の制作で演技しているときとでは、『全く人格が違う』というところに日々驚かされています。iUでは起業や自立を促すカリキュラム、理念を伝えていますが、なかなか授業中は殻を破りません。ところが、自分たちで脚本を作って自分たちで演技をしていると、『この学生には、こんなポテンシャルがあったのか』と思えることがあります。そこまでのめり込んで演技をしているのでしょう。ある意味、AIショート動画には、関わる人たちを熱狂させる力があると思っています」。
石戸:「学ぶこともたくさんあるわけですね」。
志村氏:「そうですね」。
AIショート動画を全員が表現者になる1つのフォーマットやきっかけに
石戸:「今後、AIショート動画をどのように社会に展開していきたいと考えていらっしゃいますか」。
志村氏:「映画からテレビ、テレビからYouTube、漫画からウェブトゥーンなどは新しい世代のための新しいメディアです。こうしたメディアは、テクノロジーの進歩と一緒に進化してきています。ショート動画はテレビ番組などと比べて時間が短いから『ショート』という名前が付いていますが、否定的な意味でのショートではなく、ショートがこれから一般的な言葉になるかもしれません。新たな名称が付くかもしれません。ショート動画には、人間がクリエイティブになったときに最も熱狂する時間の過ごし方のひとつになる可能性があると感じています。AIショート動画は全員が表現者になる1つのフォーマットやきっかけになると思っています」。
石戸:「AIが出てきたことでコンテンツを量産してくれるようになります。そんな時代のクリエイティブとは何であるとお考えですか」。
志村氏:「現時点ではAIが作るスライドや脚本は、自身の感性と少しずれるものが出てくることが多くあります。私は今の段階では、自分の感性ではなく、AIが作ってくれる表現に委ねたほうがいいと考えています。自分の感性にこだわり過ぎてしまうと、せっかくの時短を生かせなくなってしまいます。まずはAIが作り出す大量のものに、自分のセンスも委ねていきます。
そのうえで、日本の1億人や全世界の80億人がそれぞれ進化していくと思いますので、そこからさまざまなものが出来ていくと思います。今はAIが提示したものに、まずは自分の感性を任せる感覚が必要かなと思います」。
石戸:「AIを使う新しい制作スタイルの模索、新しい表現様式の開拓、さらにはそれらを通じた新しい映像業界のビジネスモデルの構築にチャレンジするプロジェクトであることがよくわかりました。志村さんがこれからiU B Labで取り組みたいことは何でしょうか」。
志村氏:「ショート動画をやりつつも、墨田区という場所に敷地があって、スタジオやキャンパス、校庭もありますのでリアルなイベントをやってみたいと考えています」。
石戸:「リアルなイベントという話もでましたが、iUでは社会とどう繋がりながら新しいプロジェクトを作っていくかを大事にしていると思いますし、そのためにB Labでも産官学連携のプラットフォームを作っているところです。最後に、産業界、そして社会に向けたメッセージを一言お願いします」。
志村氏:「これから大事なのは、1つの自分のエリアというか、リアル、バーチャル含めて自分が根ざす場所を1つ持つことだと思います。そのうえで、そこにとどまらないで、あるいはそこにこだわらず、どんどん移動していくことが大事だと思っています。人間のクリエイティビティや想像力は移動距離に比例すると言われていますが、墨田区や東京をベースにして、さまざまな業界やエリアと繋がっていくことが面白い生き方に繋がると思っています」。
