【iU B Labプロジェクト紹介】 「きっかけ」を探り「一歩目を踏み出し」 実際に『お金を稼ぐ』
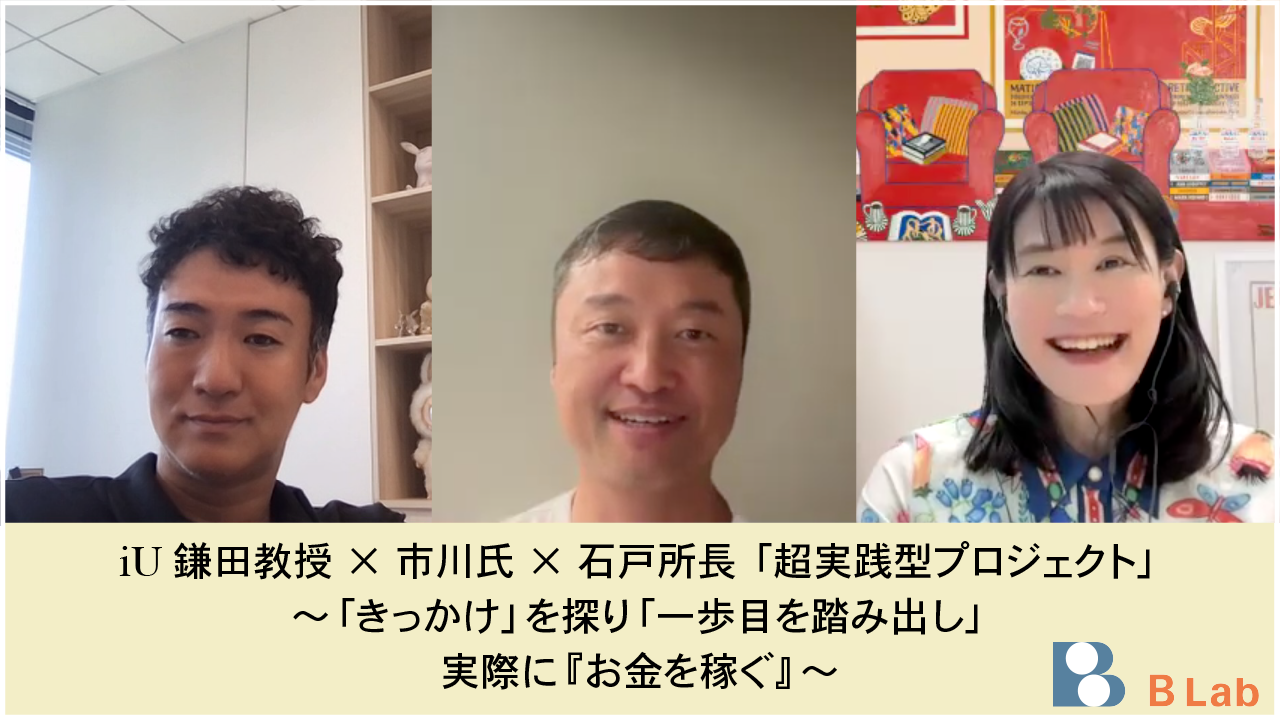
iUは、ICTやビジネススキルを活用して社会課題を解決し、世の中に新しいサービスやビジネスを生み出すイノベーターを育成する大学です。その研究所であるB Labでは、iUの教員が主導する多彩なプロジェクトが日々進行しています。
今回は、iU教授でKMD株式会社 代表取締役社長/UUUM株式会社創業者の鎌田 和樹氏(▲写真1/下)とKMD株式会社 取締役の市川 義典氏(▲写真1/上)にお話を伺いました。鎌田氏が中心となって進める「超実践型プロジェクト」は、ビジネス現場のOJTに近い取り組みを通じて、実際にお金を稼ぐことを学びます。実践的なビジネススキルのみならず人間力も重視したプロジェクトについて、B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真1▲)が、深掘りしました。

「実際にお金を稼ぐ」ことを学ぶ
超実践型プロジェクト
石戸:「本日は2025年4月よりiUの教授に就任された鎌田 和樹さんにお越しいただきました。鎌田さんは、クリエイティブエージェンシーのUUUMを創業し、ユーチューバーを『国民的な職業』として認知させたことでも知られています。現在は、おもに経営コンサルティングを手がけるKMD株式会社の代表取締役社長でもいらっしゃいますね。また、2024年に上梓された著書『名前のない仕事- UUUMで得た全知見』は私も拝読し、ぜひ学生にも読んでもらいたいと思いました。そんな鎌田さんが、iUで取り組んでいるプロジェクトとは、どのようなものでしょうか」。
鎌田氏:「プロジェクトの名称は『超実践型プロジェクト』です。私は19歳で社会人となって、29歳でUUUMを立ち上げました。これまでを振り返ると、社会人になり会社員として過ごした年月があったからこそ、今の自分があると思っています。以前にiU学長の中村 伊知哉氏にお会いしたとき、私は『iUは確かに起業率がとても高い大学ですが、学生が起業しても成功する確率はほとんどないと思っています』と話しました。というのも、学生のほとんどは、自分自身でお金を稼いで生きていくことがいかに大変かを社会に出て学ぶ経験をしていないからです。それでは、どうすればそうした学びや経験ができるのか。私は、『OJTこそが全て』だと考えています。そこで、私のプロジェクトでは、ただ単純に教員の話を聞くだけではなく、『実際にお金を稼ぐ』ことを学生にも実践してもらいます」。
石戸:「とても興味をそそられるプロジェクトですね。『超実践型』とありますが、具体的にはどのようなことに取り組むのですか」。
鎌田氏:「私は今、KMDのほかに2つの会社を経営しています。一つはHONEST(オネスト)という芸能事務所で、もう一つはSITUE(シチュエ)という、SNSマーケティングやインフルエンサーなどのキャスティングを手がける会社です。学生たちには、これら二つの会社の社長や役員、もちろん私からも実際のビジネスを通じた実践的なことを直接、学んで欲しいと考えています。具体的には、『どういうことが今、世の中では求められているか』をしっかりと考えていただきたいのです。例えば、芸能事務所のマネージャーのイメージは、以前でしたら付き人のようにタレントの後ろについて回る仕事というものでした。今でも、そういった仕事を求められることはありますが、今のマネージャーは、それだけをやっていれば務まるものではありません。
テレビでタレントをキャスティングするとき、ビジュアルが良いことやどこの芸能事務所かといったことが判断材料になりますが、今ではフォロワー数が多いことが重視されます。重要視されるポイントが変わってきていて、それらを踏まえて、芸能事務所もマネージャーもタレントを売り込んでいかないとなりません。マネージャーは、テレビ局やタレントから言われたことだけをこなす『御用聞き』であれば良い時代ではないのですね。そうしたことを実際に学んでもらいたいと考えています。もう一つのSITUEは、市川さんが代表を務めています。市川さんから説明していただきます」。
市川氏:「SITUEは、SNSマーケティングとコンテンツ制作を軸に事業を展開しています。私はコンテンツ制作、マーケティングに長い間、携わってきたので、その経験・知見を学生に還元し、学生と一緒に想い出に残るような経験ができれば素晴らしいと考えてプロジェクトに取り組んでいます。
コンテンツ制作においても、時代の変遷の中で求められるものが変わってきています。最近ではオーディション番組が増えて、オーディション番組からデビューするタレントは、その時点でファンとの強力なエンゲージメントを作り上げています。ファンがタレントやグループを応援し、育てていくような構図、そういったスキームを作ったうえでデビューさせることで人気が出たり、コンテンツとして面白くなったり、受け入れられたりする時代だと思います。こうしたことを、講義を聞くだけではなく、実際に学生と一緒に経験していくことを大切に考えてプロジェクトを推進しています」。
「嗅覚」「一歩を踏み出す」
そして「自分の意思で決断する」
石戸:「お二人のお話に共通しているのは、既存の枠組みにはとらわれない『新しい価値の創造』だと感じます。その実践にあたって、大切にしている視点や行動指針などを教えていただけますか」。
鎌田氏:「私も含め、みなが起業家や発明家ではないと思います。私にしても、ある日、突然に『UUUMを作りたいと思いました』といったことではありませんでした。ニーズというのか、UUUMを作るきっかけがありました。『クリエイターが困っていました。それをたまたまサポートしようと思いました。やってみたら、困っている人がさらにたくさんいました』といったことで、このように何かが生まれるきっかけは身近なところにあると思っています。そのきっかけを見つけ出せるかどうかがポイントで、それに対する嗅覚が大切だと考えています。嗅覚を鋭くするには、やはり常にアンテナを張って情報収集をしておくことも大切です。そして、何かきっかけがあったときには、さっと一歩目を踏み出せるようにする、そのことは大切にしています。
また、『決めること』もすごく大切です。先ほど話した中では、『困っている人がさらにたくさんいました』となった時に、『そうか。頑張れよ、お前たち』と言うこともできたでしょう。そうしたときに事務所を立ち上げようとなったのは、『こうしていきたい』、『こうしよう』と自分で決めたからです。決めたから、結果的にユーチューバーをたくさん束ねることになり、それを世の中の人たちが見て『ああ、ユーチューバーの事務所だね』と言うようになったのです。グローバルベースで見たら『エージェンシーに近い』と言われることもありました。事務所やエージェンシーや、いったい何がぴったりくるかは、じつは当事者は考えていなくて、私にしてもただ単純に『こういったビジネスをやっていきたい』ということを心に決めて歩んできただけです。嗅覚を鋭くして、きっかけを嗅ぎとったら一歩を踏み出すこと、その方向だけを間違わなければ、新しい事業は生まれると思います。
例えばメディアをキーワードに新しいビジネスを立ち上げるとした場合、学生の多くは『旧来からあるメディアを踏襲しながら新しさを打ち出す』のか、『これからの新しいメディアを作る』のか、どちらかから考え始めるでしょう。ところが、実際のビジネスでは、単純な二者択一ではなく、『結局、今、世の中から求められていることは何か』をきちんと考えることが、とても重要になるのです。『過去を否定して未来だけ』ではなく、過去と未来を否定も肯定もせずに、ただ求められていることは何か、自分がやりたいことは何かを真摯に考えていったほうが最終的にはビジネスに繋がっていくと考えています。
新規ビジネスとなると新しい市場を探すことやTAM(獲得可能な最大市場規模)の大きなビジネスを考えるといったことが言われますが、新しい市場やTAMが大きなビジネスがまだあるのかというと、そうではないのが現実です。だからこそ、求められていることは何か、自分がやりたいことは何かを考えて、そこからスタートするほうが、そのビジネスにかける想いも強くなるでしょう。『儲かりますよ』と言われて始めたビジネスより、『これが好きだから』のほうが最終的には続くと思いますし、私はそういう人を応援したいのです」。
石戸:「既存の価値観にとらわれる必要はない、ただし、それを否定して新しいものを作るという考え方も既存の枠組みにとらわれているというご指摘はまさにそうですね。大切なことは、素直に何が求められているかを見極めること、というのもおっしゃる通りだと思いました。お話しの中で『嗅覚』、『一歩を踏み出す』、そして『自分の意思で決断する』というのがキーワードと感じたのですが、それらはいずれも生成AI時代の今にこそ求められる人間の力でもありますね。これまでも重要な力であり、これからさらに求められる力だと思います。市川さんは、新しい価値の創造という視点で大切にしてきたこと、行動指針としてきたことはどのようなことでしたか」。
市川氏:「私は経営者としての経歴は、それほど長くはないのですが、やはり、『自分で決める』ことを大切にしていますね。そのうえで決めたことに対して、『動けるのか』、それを『続けられるのか』、これらを常に自問自答しています。自分から動くことができて、それを継続できるのであれば、どこかのタイミングでターニングポイントがやってきて成功に繋がっていく、成功に導かれていく、目標や目的が成し遂げられるのではないかと考えています。
もう一つ、私が大切にしているのは、石戸さんもお話をしていた『人間』という言葉です。AIや生成AIの発達・発展が目覚ましい今、シンギュラリティもまことしやかにささやかれています。そういう時代にあって、『人間だからこそできることは何か』については、最近、とくに考える機会が多くなっています。そのことを常に考えながら仕事をしているような気がします。
AIや生成AIで業務改善が図られたり、業務効率が向上したりすることはこの先も増えてくると思います。その一方で、実際に農業で米を作る、その米を届けるといった農業や配送業などの仕事には、AIや生成AIだけでは解決できないような課題が、まだまだ数多くあるでしょう。そこを人間の手を介しながら改善していく、より良いものに変えていく、AIや生成AI時代の今だからこそ、そこに光を当てて新しいビジネスモデルを考える、そして、自分で決めて動き、それを続けられるようにしていく、そんな取り組み方をすること、そこを大切に考えています」。
石戸:「今、『人間だからこそできること』、人間としての力についてのお話がありました。これからの時代には、人間力、人間としての魅力が今まで以上に求められると思います。お二人は、iUのプロジェクトで18歳から22歳の学生たちと触れ合っていますが、学生たちに『どのような力を育んでもらいたい』、『どのような力がこれからますます必要になる』とお考えでしょうか。このプロジェクトを通じて学生たちに伝えたいことを教えてください」。
鎌田氏:「否定的なことのように聞こえるかもしれませんが、じつは、このプロジェクトを通じて新しい力が養われるとは、あまり考えてはいません。やはり、あくまでも学業の中の一環です。これから先に何かを築くきっかけになれば良いと考えています。社会人になった時に、『そういえば、iUの教員はこんなこと言っていたな』と少しでも思い出してもらい、失敗する確率が下がって成功する確率が上がってくれれば良いのです。それ以上を望むのは、なんとなくエゴのような気がします」。
石戸:「先ほど、『好きな気持ちを大切に』というお話もありましたが、きっかけはとても大事ですね。『名前のない仕事』の中でも『誰かの一言が背中を押してくれることを大切にしている』といったことが書かれていて、印象に残りました。自分が一歩を踏み出すきっかけが大切だと考えると、そのきっかけを提供してくれる場を作っていることは、素晴らしいです。市川さんは、プロジェクトを通じて学生に伝えたいことは、どのようなことですか」。
市川氏:「前段でお話した内容と真逆のように聞こえるかもしれませんが、コスト意識です。もちろん新しいビジネスを立ち上げるにあたって、自分の想い、動くこと・動けること、継続すること・継続できることは非常に大切ですが、どのような事業を起こすにしても、何を行うにしても、どうしてもお金がかかるという現実を受け入れることはとても重要です。それを受け止めてシミュレーションしていかなくてはなりません。人を雇うのにもお金がかかりますし、コンテンツを編集するのにもパソコンやソフトウェアが必要でそれを購入するにはお金が必要です。撮影するならカメラ機材が必要となり、その機材が壊れたら新しい機材を買うコストがかかります。
さらに、競合相手が良いカメラ機材を購入し、プレゼンで高いクオリティの提案をしてきたとなれば、それと戦っていくためには、より良い企画やより良い機材なりが必要となるでしょう。やはり、コストは切っても切れません。想いだけでは、どうしても実現できないことに直面するのが実際のビジネスの世界なのです。そういったことも現実的に伝えながら、きちんと学生たちの想いが具現化、体現化できるように背中を押せたら良いと考えています」。
iUは企業との「距離が近い」
OJTに近いプロジェクトを実践できる
石戸:「『こういうものがあったらいいな』という夢を現実に落としもうとすると、そこには大きな乖離があるというのが現実ですよね。そして、そのギャップを少しずつ埋めていくプロセスこそ、アイデアを生み出す以上に難しく、大変な部分なのかもしれません。そうした現実を学生たちにしっかり伝えようと、プロジェクトに取り組んでいらっしゃるのですね。
お二人はこれまで、UUUMの立ち上げをはじめビジネスの世界で大きな成果を収めてこられました。そのお二人が大学に関心を持たれたきっかけは何だったのでしょうか。また、大学だからこそできることとして、どのような可能性があるとお考えでしょうか。ぜひお聞かせください。
鎌田氏:「私は既にデジタルハリウッドで客員教授として、期間限定でゼミを開講し、単位を認定することは経験していました。ただ、長いスパンで教授を務めることは初めてです。私のように大学を卒業していないのに教授になるというのも、世の中としては、もしかしたら面白いのではとも感じました」。
石戸:「実際にiUで教授として活動されてみて、どのように感じていらっしゃいますか。大学はビジネスの世界とはまた少し異なる空気感を持つ場だと思いますが、大学だからこそ挑戦できること、そして民間企業だけでは実現し得ない可能性について、どのようにお考えでしょうか」。
鎌田氏:「『大学』という言葉は、便利に使えるところがありますね。シンクタンクに近いイメージを持たれることもありますし、『大学でそれを研究しています』と言うだけで世の中の扉が開くこともあります。超実践型プロジェクトとは、また別の話になりますが、私自身がそんな大学の持つ特性や可能性にもう一歩踏み込んで、もっとうまくiUを使いこなせるようになったら面白いことができると感じています。
また、学生だからできることもあると思います。そんなに高望みをする必要はまったくなく、例えば、学生時代に起業してみて、また別に就職してみて、その後にまた起業を繰り返すといったことをしても良いでしょうし、『起業してみたが、どうも自分が目指していたのと違うと思うので、そのまま海外行きます』も正解だと思います。若いことは無限大の可能性があり、力を秘めているのです。それだけは否定したくないと思っています。『なんでもやってみるといい』というのは無責任にも聞こえますが、それに近い考え方で接したほうが、結果的には目指しているところにたどり着くのではないかという気がしています」。
石戸:「鎌田さんがiUを使いこなした先に何が生まれるのか、その世界を見てみたいです。市川さんは、大学だからこそできるチャレンジ、可能性について、どうお考えですか」。
市川氏:「私は教員免許を持っていることもあり、学生に授業ができるということ自体がとても貴重な機会だと考えています。自分の仕事を考えても、産学連携で学生の授業を担当できることは、とても有意義で非常にモチベーションが高い状態ですね。
マーケティングでは、さまざまな調査をもとにターゲットを設定し、プロダクト設計やプロモーション設計をしていきます。その際、市場的な価値が高いZ世代やアルファ世代と呼ばれる人たちが、どういうことを考えていて、どういうものに興味があって、どのようなビジネス展開を考えているのかは、なかなか把握するのが難しいところです。学生の皆さんと壁打ちしながら、何か新しいもの、既存ビジネスを変えるような新しい発想、それらを考えて形にできたら非常に面白いなと期待しています」。
石戸:「コロナ禍や生成AIの登場といった社会の大きな変化を中高時代に経験した世代が、いまちょうど大学生となっています。そうした学生たちは、どのような価値観で今を生きているのか、新しい価値観を持った学生たちと一緒に新しいものを生み出すことができる場として大学は非常に面白い役割を担えるのではないかとお話を伺いながら思いました。
鎌田さんは『OJTこそが全て』とおっしゃっていましたが、19歳で社会に出られた鎌田さんは、同世代が大学を卒業する頃にはすでに実務経験を積まれていたことと思います。以前であれば、大学で4年間を過ごした学生を企業に迎え入れ、入社後にOJTで鍛え直す余裕が企業にもあったかもしれません。しかし今の時代、その余裕は失われつつあります。そう考えると、大学がその役割を担い、『失敗も許される大学の4年間』で徹底的にOJTを実践することには大きな意味があることだと思います。その点について、大学と企業との新しい関係性や、大学がこれから果たすべき役割について、どのようにお考えでしょうか。」。
鎌田氏:「まず、iUは特別だと思います。他の大学と違って、よりOJTに近いことを実践しています。iUと企業との距離感は、他の大学と企業との距離感よりもずっと近いでしょう。ただ一方では、どの大学でも4年間を遊び呆けて社会人になる人は、以前と比べてずっと減ってきていると思います。私は大学に行っていないので、そういった人たちやそういった環境を羨ましいとも思ってしまいます。
高校生や大学生のときに作った友人は、一生付き合い続けことができる仲間でもあります。そういう仲間たちと遊ぶのも大切ですし、社会人になる前の最後の時間でもあります。そういう意味では、自分にとって納得できる時間を過ごせるなら、遊びであっても、それでいいという気がします。
私が19歳から働いていたことが結果的に良かったのかというと、今はもちろん『良かった』と言えるのですが、一方では大学時代の仲間が私にはいませんので、人間として自分を見つめたときに少し寂しいと思うことはあります。それ以上に仕事仲間がいるから良いのですが、『同い年』や『同期』というのはまた違ったキーワードやパワーワードになりますよね。私は結果的に大学の同期というのが少なくなってしまったので、学生たちには全体のバランスを考えながら大学生活を過ごし、社会人になり、企業に勤めるようになってもらえればいいなとは考えています」。
石戸:「以前の学生と比べると、今の学生たちは大学4年間の過ごし方において、より多様で幅広い選択肢を持っています。だからこそ、自分でどのような4年間にするのかを主体的に選び、その選択を自らの正解にしていく力が一層重要になっていると感じました。市川さんは、大学と企業との新しい関係性や、大学がこれから担うべき役割について、どのようにお考えでしょうか」。
市川氏:「私が、採用に関連して学生たちを面接する機会が多くありましたので、そのときのことを踏まえてお話します。学生のみなさんに『最後に何か聞いておきたいことはありますか』と尋ねると、ほぼ全ての学生たちが質問してくるのが『大学を卒業し就職するにあたって、何をしておけばよいでしょうか』というものでした。それに対するこちらの答えはシンプルで『学生だからこそできると思うことをやってください』です。
SNSマーケティングやマーケティングでは、マスが何を求めているかという視点も、ターゲットを絞り込んだニッチな領域の人たちが何を求めているのか、というようにいくつもの視点を持つことが求められます。就職にあたって企業が学生に求めることは当然、ありますが、それはあくまでも企業側の視点です。それだけではなく、学生として、『学生だからこそ、就職する前にしておくべきだと思うこと』という学生側の視点もあるはずです。さまざまな視点で、さまざまな人たちがどのようなニーズを持っているのか考えることが大切です。そうした企業側からだけではない、さまざまな視点を考えられる場が大学であると思います。
大学の可能性や新しい役割について考えると、iUは起業したいという思いのある学生がほとんどだと思います。それは素晴らしいことですし、その仲間が今、数十人、数百人もいる状態なのです。やりたいことは、一人ひとりバラバラであっても、皆さんが今、同級生としてコミュニケーションを取りあっていると思います。今は、『やりたいことがバラバラ』の皆さんが、起業して、取り組みを継続させていく中で、それらが繋ぎ合わさってシナジーが生まれる、そんな事業が生まれてきたら、これほど楽しく拡張性があるものはないでしょう。iUのそんな可能性に、そんな役割を担うことを期待しています。そういったことからも、皆さん、友人や同級生の方々とコミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか」。
学生が起業するのが当たり前となるような
新しい大学の形を作っていく
石戸:「B Labとしても組織の枠を超えて、さまざまな機関と連携をしながら共創していくことを大事にしています。学生のみならず、iUには数多くの客員教員や連携企業が参画しています。これから先、そういう他の教授陣や企業、組織を巻き込んでいくという構想はお二人の中にはあるのでしょうか」。
鎌田氏:「『ないことはない』と思っています。段階やステップの問題ですが、iUには『ノーはない』と感じています。私たちも『教授1年生』です。まずは地に足をつけて、一つひとつこなしていきたいと考えています」。
石戸:「市川さん、どうですか」。
市川氏:「当たり前ではないシナジー効果に期待しています。『こういう事業とこういう事業をくっつけたらこんなになるよね』というようなものではないことです。絵空事かもしれませんが、その絵空事を、コスト意識を持ちながら実現できればiUの学生は誇りを持てる仕事ができるでしょう。そんなことが一緒にできたら良いなと思っています」。
石戸:「最後に一言、今後の展望や、社会に向けてのメッセージを一言いただいてお終いにしたいと思います」。
鎌田氏:「iUを通して私自身も勉強させてもらうことも多くあります。私の主導するプロジェクトが、学生の皆さんにとって、『なんとなく良かったな』と思ってもらえる時間になれば良いなと考えています。
以前は、東大発のベンチャー企業が多くありましたが、現在はiU発のベンチャーが多くあります。学生の起業を促すiUのような大学の存在が当たり前のようになり、大学の枠組み自体が良い形で壊れていき、新しい時代に繋がっていく、iUはそのきっかけになりつつあると感じています。そうした動きをさらに加速させようと、私も市川さんもプロジェクトに参画しています。ぜひ、一緒に取り組んでいきましょう」。
市川氏:「AIや生成AI、ロボットやシステムではない、『人が何か介するような仕事』が今後、学生の皆さんが就職や起業する上での大切なポイントになってくるでしょう。AIやロボットやシステムだけで全てを解決するのではなく、人の手を介す何かをビジネスの中に組み込んで、『この事業は自分でなければできないんだ』というものを考えていただきたいと思います。プロジェクトを通じて、その実践を支援していきたいと考えています」。
石戸:「日本では、初等・中等教育の仕組みが150年もの間ほとんど変わっていないと言われています。しかし今まさに、従来の教育のままでは対応しきれない課題が次々と明らかになってきています。抜本的な改革が求められる中で、私自身も新しい大学のあり方を模索し、創り上げていくことに取り組んでいます。ぜひお二人を含め、iUの教授陣の皆さまとともに、こうした挑戦を進めていきたいと考えています。本日は貴重なお話をありがとうございました」。
